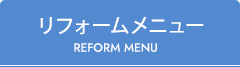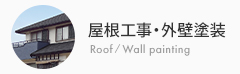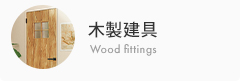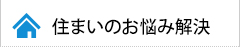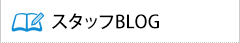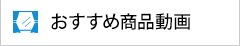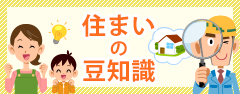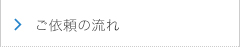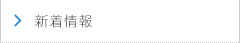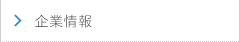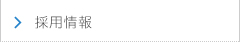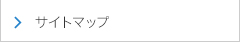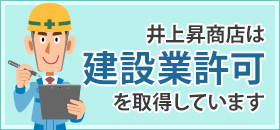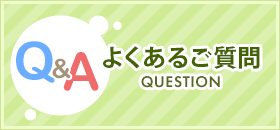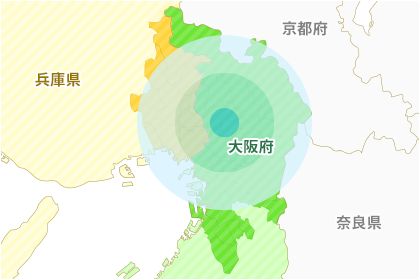豊中市にて築30年以上は経過している木造平屋の屋根瓦が強風を受けて飛んでしまった。


早速、西宮市にて築30年ほど経過されている木造平屋にお住いのお客様宅にお伺いさせて頂きました。
お客様が気付かれた場所からもう一度屋根瓦の状態を確認しました。
瓦がガタガタと傾いていたり、ズレていたりしているのがわかりました。
実際屋根瓦に登って近くで被害状況を確認していきます。

お客様がご心配されていたのは、瓦が浮いているズレている箇所がお隣様の壁のすぐ近くに位置しているからでした。
このままの状態で、台風や強風が発生してしまうと、高い確率で瓦が飛びお隣の壁に被害がおよびそうです。

屋根瓦の被害状況は確認できました。
それにしてもなぜ、この部分の瓦だけが飛んでいってしまったのか不思議です。
お客様からお話を聞いたところ、20年以上前の大震災の時にお家を建てたころから使用していた屋根瓦が震災の被害を受け、ほとんどの瓦が使いものにならなくなったとのことでした。

お話を聞いたあとにもう一度だけ瓦が飛んで無くなってしまった箇所を確認しに行きました。
そこで気になったのが、瓦が瓦桟に固定されている形跡が見当たらなかったことです。
通常、屋根瓦から新しい屋根瓦に葺き替える場合は、
もともとあった瓦を撤去する⇒葺き土・防水紙を撤去する⇒野地板の状態にする⇒野地板の上に新たにコンパネを敷く⇒防水シートを敷く⇒瓦を固定するための瓦桟を取り付ける⇒ステンレスの釘を使用して瓦を瓦桟に固定させる

ただ瓦を打ち付ける適切なガイドラインがないのも事実になります。
【対応の方法を考える】
1時間ほどで現場状況の確認が終了しました。
防水シートや瓦桟が露出している状態をそのままにしておくと雨がふった時に雨水が防水シートや瓦桟を傷めてしまい被害が拡大していくので、一旦、残っていた瓦をもとの位置に戻して蓋をしておきました。

①割れている瓦数枚を用意して、もとの場所に戻す方法。
一番簡単で費用も抑えれます。
ただ注意したいのは、戻しただけなので、また同じような台風が来た時には飛ぶ可能性は非常に高いです。
②釘の打ち直し
飛んだ瓦の周辺の瓦を一旦外して、もう一度屋根のてっぺんから下(軒先)にかけて瓦桟に瓦を打ち直していく方法です。
どちらにしても準備に日数がかかるため、雨の被害を少しでも無くすために屋根に養生をすることになりました。
不安に感じる内容によって修繕方法を選んでいくことがより満足した結果につながると思いますので、色んな方法を提示してくれる業者を選ばれることをおススメ致します。